浮世亭三吾・十吾

浮世亭三吾・十吾(右)

浮世亭三吾・十吾(右)
人 物
浮世亭 三吾
・本 名 沼口 正利
・生没年 1943年12月14日~2025年10月25日
・出身地 大分県 中津市
浮世亭 十吾
・本 名 田野 重喜
・生没年 1950年3月3日~2014年末
・出身地 島根県 浜田市
来 歴
浮世亭三吾・十吾は戦後活躍した漫才師。明るく品のいいしゃべくり漫才で昭和の漫才ブームの若手として活躍。三吾は後年娘の美ユルとコンビを組み、日本で数少ない親娘漫才を率いていた。
三吾は大分県中津市の出身。ただ、若い頃は福岡県出身といっていたこともある。相羽秋夫『上方演芸家名鑑』によると――
本名沼口正利。一九四八(昭二三)〜
福岡県吉備中卒業後来阪。住友金属に勤めるかたわら明蝶学院に入り、浮世亭とん平に入門。昭四四年千日劇場で十吾と初舞台を踏む。3×5= 15という変った名が話題を呼び、万国博覧会でも大活躍した。昭四六年第二回NHK上方漫才コンテスト優秀敢闘賞、翌年第七回上方漫才大賞新人賞を受賞した。少林寺拳法二段である。
一方、LP『やんぐ寄席』の解説では(松竹文芸部の重里正雄が執筆)――
「サンとゴ、あわせて三吾・十吾デース」 高座に出たとたんにお日さまが顔をのぞかせたよう。明るく健康的である。めがね、背のひょろ長いおとこが十吾。ちんまいずんぐりおとこが三吾。現代ッ子、若手らしく声のデッかき、ひょうきんき、それに舌の回転の早さ、などがコンビの個性ともいえようか。「NHK漫才コンテスト」と「上方漫才大賞」 (ラジオ大阪)では47年春、ともに“新人賞” のダブル賞を受賞という栄光をキャッチした。 人気、質とも上昇路線にある。しゃべくり漫才の正統派。
三吾。昭和23年、福岡県の生まれ。中卒後八百屋の御用ききをふりだしに、電気工事人、 牛乳配達など転々。18歳のとき大阪へ。漫才に魅せられて明蝶学院に入った。相方、十吾とのなれそめはここ。そしてコンビを結成した。声のデッカさは彼、少林寺拳法二段によるものだ。
十吾。昭和25年、島根県の産。のち神戸市立御影高校を卒業。三吾と同様に漫才志望が実を結んだ。学生時代は陸上選手で、体の柔らかさもそれによる。根っからの陽性だ。スポーツマンの共通性、もち健康管理である。
「健全なる笑いは健全なる体に……」てな論法をモットーに、体力ずくりに汗を流している。寒風吹きすさぶ夜の御堂筋で、トレパン姿の青年2人をみかけたら、まず彼等だと思えばまちがいなし。神社境内でも「ヤー」 「オウー」の声が飛べば、拳法けい古中の三吾だ。舞台での飛び、はね「まかしときなさい」 と張切るコンビ。目標はやはり間(ま)あいのうまいしゃべくり笑芸。そして「才界天下を先取りしたいんです」と口を揃える。その理想に向って大きな跳躍が期待される。
1968年、上京して曾我廼家明蝶が経営していた芸能塾「明蝶学院」に入学。ここで知りあった田野重喜と意気投合し、漫才コンビを結成。浮世亭十吾の経歴は以下の通り(演芸家名鑑)――
本名田野重喜。一九五〇(昭二五)~
神戸御影工高卒。すぐに明蝶学院に入り、三吾と知り合い、とん平門下で昭四四年初舞台。くいだおれの人形みたいな顔が笑いを呼ぶ。賞は浮世亭三吾の項を参照。
なお、十吾の出身地は島根県浜田市であったという。
意気投合した二人は浮世亭とん平を紹介され、彼の門下生となった。「三×五=十五」という洒落から「浮世亭三吾・十吾」と名付けられる。同年千日劇場で初舞台を踏んだが、間もなく松竹芸能へ移籍。三吾は50年にわたって同社に所属。
1970年3月、大阪万博の電気通信館で行われたショーでは狂言回しの一組として採用され、毎日のように電気館で漫才を披露したという。さらにテレビ電話の実演なども行い、華々しいスタートを切った。
獅子舞そっくりの愛嬌ある三吾とひょろっとして食い倒れ人形そっくりの十吾の飄々たるコンビで人気を獲得。
1970年代にはすでに角座の舞台を与えられるなど、実力派コンビとして売れに売れていた。
1972年3月、第2回NHK上方漫才コンテストに出場し、優秀敢闘賞を受賞。優勝は中田カウス・ボタンであった。『NHK年鑑1972年度』に――
昭和45年度にひきつづいて第2回上方漫才コンテストを開催、参加した23組の新人コンビのなかから、優秀話術賞(中田カウス・ボタン)、優秀敢闘賞(浮世亭三吾・ 十吾)、優秀努力賞(船仁のるか・喜和そるか)の三賞を選んで漫才の向上発展に資した。
1972年4月1日、上方漫才大賞新人賞を受賞。大賞は宮川左近ショー、奨励賞はチャンバラトリオであった。若手では珍しく二冠達成している。
1972年4月22日には、NHK上方漫才コンテスト入選を祝してか、『土曜ひる席』にカウス・ボタン、のるか・そるかと共に出演。『お笑い歌い方教室』なる一席を披露している。
1972年7月9日には、『笑点』にも出演し、漫才を披露している。なお、この年はブレイクした年だったと見えて、12月3日の笑点にも出ている。
その後は大阪の『お笑いネットワーク』『上方演芸会』などの演芸番組をはじめ、『土曜ひる席』『バラエティー生活笑百科』などに出演。東京にも進出した。
永六輔は1973年11月27日、紀伊国屋ホールの漫才大会で三吾・十吾の漫才がヒットを飛ばしたことを評価し、『大日本大絶讃』の中で右のように記している。
浮世亭三吾・十吾クン
この若手の漫才をさしてうまいとは思わないが、めぐり逢った場所がよかった。 十一月二十七日、紀伊国屋ホール。東京の若手漫才が二十組ほど集まった勉強会である。
上方漫才に負けられないという意気込みはいいのだが、あまりにも客席が淋しすぎた。出演者一人が十人集めれば満員になるホールである。「みて貰おう」という一番大切な精神が、見事に抜けているのだ。
そこに上方から来た三吾・十吾、アッサリさらってしまった。異質だったから目立ったのではなくて、数が少なくとも客を客として敬っていただけのことだ。
淋しい客席に向って「超満員のお客様」とか、「客よりも出演者の方が多い」といった言葉を口にする若手はすでに若手以前に駄目な芸人である。
満員にすることが「笑い」にとってどんなに重要な要素か考えてほしい。その努力をしなかった東京の若手漫才諸君は、その根性たるや、すでに名人。
となれば東京漫才名人会だったのか。
三吾・十吾のコンビが名人でなかったことは本当に素晴しいことだった。
1976年2月28日、娘の美ゆるが誕生。後の相方である。
コンビとしては非常に礼儀正しく、行儀に厳しい落語家や講談師からも信頼されるほどであったという。四代目旭堂南陵は『小南陵のおもしろ芸人列伝』の中で――
浮世亭三吾・十吾さんのコンビは、演芸のメッカ角座を中心に活躍してはります。このコンどは、まじめを絵にかいたようなコンビです。仕事を頼んでも、
「今、仕事が終わりました。おおきに」
という報告の電話をくれます。昔は、当たり前のことだったんですが、電話一本かけることすらできない芸人が増えました。中堅の漫才師として、若手のけん引車になってもらいたいものです。
とその行儀正しさを褒めている。さらに当時の漫才師としては珍しく仲が良好なコンビだったそうで、相羽秋夫『上方演芸落ち穂拾い』の中で――
かけ算する仲の良さ浮世亭三吾・十吾
かつて、『脱線トリオ」の一員だった八波むと志は、八×八=六十四をもじった芸名だ。
また、『あきれたボーイズ」の出身で、晩年渋い役どころで人気のあった山茶花究も、三×三=九を巧みに漢字にアレンジしている。
ある中堅の地位にきた浮世亭三吾・十吾はこうした先輩の例にならって二人でかけ算をする仲の良さである。
もっとも、この芸名は師匠の浮世亭とん平が付けたもので、意外や字を見た感じの並びもスマートで、 まずは幕内で好評の名前だ。
漫才の名前は二人続けるとはじめて意味のわかるものが多い。いとし・こいし、セント・ルイス、うれし・たのし、チック・タック、千夜・一夜、てんや・わんや……。
三吾・十吾もそうした二人で一対の、もうコンビを変えては商売出来ないような宿命を負わされたような名前なのだ。
そのせいか、ともかくコンビの友情の絆は堅い。
彼らと同年輩にたかし・ひろしや廃業したのるか・そるかがいるが、このクラスでは群を抜いたコンビネーションの良さである。
芸の方も二人の息はぴったりと合って技術的にも高い。ところがこのきれいすぎる芸がマイナスして、もう少しアクが出てくれたらスターダムに乗れるのにと、心配する人が多い。
本当に漫才芸は数でむつかしいものだと彼らを見ていてつくづく思う。
1970年代後半から1980年代にかけては角座や松竹座などの漫才小屋で活躍。時にはトリを取るなど、人気コンビとして第一線を走っていた。
1989年、十吾の体調不良や両方の諸事情などもあり、コンビを解消。十吾は引退した。
なお、浮世亭十吾は引退して静かに繰り返していたが、2014年暮れに没したという。三吾の娘・美ユル氏が「その十吾師匠、昨年の暮れに亡くなられました。」とブログの中で記している。
解散後は、浮世亭ケンケン・ジョージとして活動していた小川ジョージとコンビを結成。
青い目の漫才として知られたジョージと異色漫才を組んだが、ジョージは酒や不行跡で既に身体を壊しており、漫才どころではなかったという。
1993年1月、浮世亭大吾・小吾が弟子入りしコンビを結成。男装をした女性の大吾と小柄な小吾という意外性のコンビで人気を集めた。
1994年1月11日、娘の美ユルとコンビを結成。
美ユルは元々子役として芸能界に出入りした経験があった上に、父が連れてくる芸人とも面識がある。その上、尼崎市立尼崎産業高校在学中に、レツゴー三匹のじゅんの付き人を2週間やったこともあり、高校時代からすでに芸能界進出の道を固めていた。
高校卒業直前に「芸人になりたい、漫才を組みたい」と直訴。父は猛反対であったが、母の後押しもあり、最終的にはコンビを組んだ。
三吾は娘とコンビを組むにあたって厳しく接し、ギャラや待遇もまるっきり別――という対応を取った。それでも美ユルは必死に食いつき、人気漫才師となった。当初は「さやかみゆる」といっていたが、後に「美ユル」と改名している。
1997年発行の『もうひとつの上方演芸』では以下のように評されている。
かつての漫才は家内工業的で、兄弟・姉妹に親子に師弟、はたまた夫婦というパターンが主流であったが、現在は少なくなった。そんな時代の趨勢に立ち向かうべく(逆行?)、このコンビは誕生した。こういうコンビは寄席に必要である。糊口をしのぐだけのコンビにはなってほしくない。男々コンビから男女コンビ、しかも親子コンビになり、三吾も、他のコンビ以上にネタや設定、やりとりに腐心すると思うが、三吾・十吾時代の財産を食いつぶす事なく、一からすべてを構築してもらいたい。大変だが。(み)
1998年頃、「浮世亭三吾・みゆる」と改名。
父娘コンビとなった後は再築された浪花座やライブなどを中心に、『上方演芸会』『バラエティー生活笑百科』などで存在感を発揮した。また、三吾は落語家と仲が良く、寄席向きの漫才を得意としていた関係もあってか、落語会のゲストとして呼ばれることも多かった。
2005年、「浮世亭三吾・美ゆる」と改名。
2008年、「浮世亭三吾・美ユル」と改名。
2011年、浮世亭一門から離脱し、「三吾・美ユル」と改名。ブログでも「そして報告いたします。今年から『浮世亭』を外しましたので今後は『親娘漫才 三吾・美ユル』でお願いします」と記されている。
なお、この事情に関しては立ち入れない。
美ユル氏が「屋号を外すということは大きなことです。私自身は入門しておりませんでしたが、師匠は40年以上も大切に愛をもって守り続けてまいりました。それを外すという事は、中途半端なことではないということだけお伝えさせてください」と記した通りだろう。
何はともあれ、三吾・美ユルと大吾・小吾は浮世亭一門を抜けることとなった。
その後は松竹芸能の大御所コンビとして第一線で活躍。関西演芸協会の重役を勤めるなど、三吾は名実ともに上方漫才の大御所となった。
2020年、大吾・小吾が師匠に先立ってコンビを解消し、引退。二人共芸能界を去った。
2022年1月頃に「浮世亭三吾」と復活させたらしく、没するまでこの名前で活躍した。
2022年4月9日、NHK『バラエティー生活笑百科』の最終回では古参出演者として出演し、漫才を披露している。
2023年12月、骨折をして休演。骨折の度合いはひどく、家族も当人も苦労の連続であったが、懸命なリハビリと介護の末に再び立ち上がれるようになり、漫才もできるようになった。
2024年5月8日放送の『上方演芸会』に出演。これが最後の上方演芸会だった模様か。
2024年7月15日、繁昌亭で復活を遂げるも2日目に体調不良を訴えて入院。数日で退院している。
最後の舞台は2024年10月31日に繁昌亭で開催された「梅團治・小梅、三吾・美ユルW親子会」ではなかったか。
その後、体調不良の悪化で血液が体に回らなくなったことや心臓病などもあり入院。長らく闘病生活を続けていた。
それでも舞台復帰を目指していたようで、美ユル氏のブログなどでは時々近況が報告されていた。
2025年10月25日夜、突如様態が急変し急逝。81歳であった。美ユル氏はブログの中で――
「あまりに突然のこと過ぎて家族もアタフタで。もうずっと入院をしておりましたが最近は落ち着いていました。ところが夜中に容態が急変し、駆けつけましたが私たちも間に合いませんでした。本人は苦しまずに逝ったそうなので良かったです」
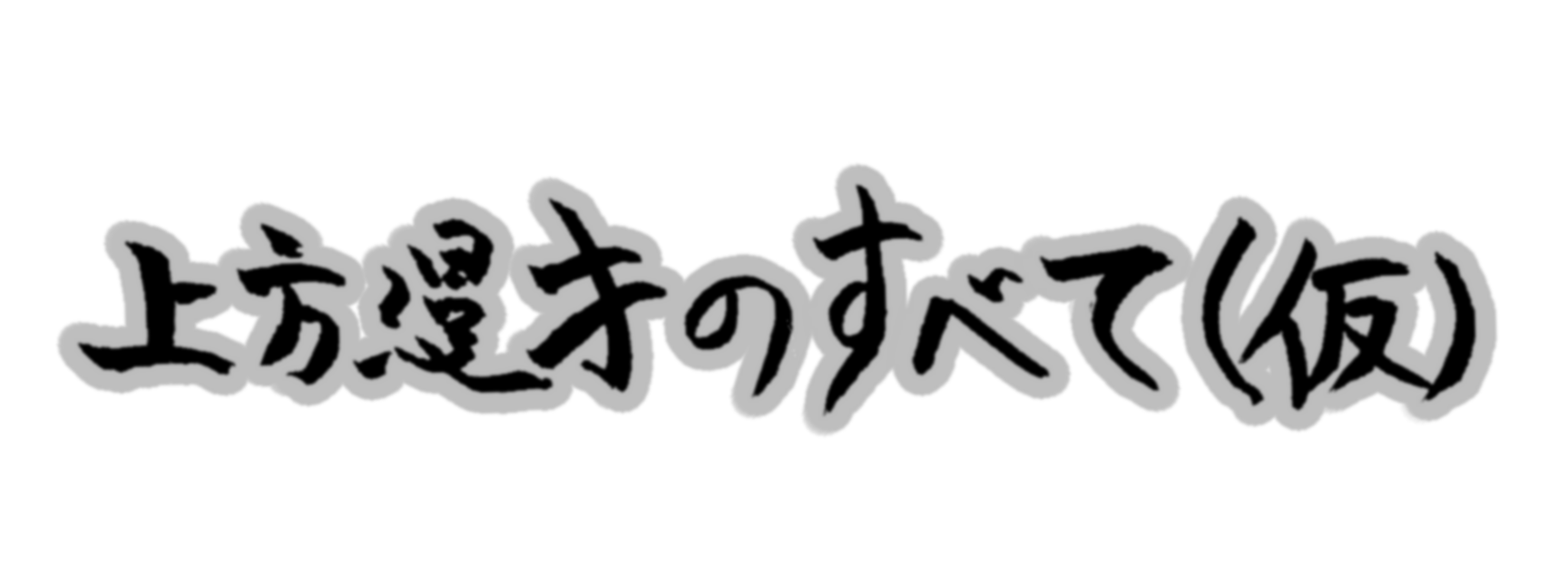


コメント