橘ミノル・双葉みどり

(関係者提供)
人 物
橘 ミノル
・本 名 西村 虎雄(後に欣也)
・生没年 1914年5月28日~1968年9月18日
・出身地 東京
双葉 みどり
・本 名 西村 マツヨ
・生没年 1921年3月5日~??
・出身地 岩手県一関(東京とも)
来 歴
橘ミノル・双葉みどりは戦後活躍した夫婦漫才。関西の中で標準語を漫才をこなす特異なコンビとして売り出し、夢路いとし・喜味こいし、島ひろし・ミスワカサと並んでホープとして期待されたがミノルは夭折、志半ばでコンビ解消した。
経歴らしい経歴は山川静夫『上方芸人ばなし』に出ている。
現在病弱で引退しているミノルは東京生まれ。浅草仁丹塔の右で生まれ、左で育った。子供の頃から芝居が好きで、六代目の俳優学校へ入学。尾上浪之助と名乗り、六代目から、松緑か浪之助と言われるほど可愛がられた。「忠臣蔵」の大序で、並び大名が引込む時、浪之助の前の役者がころんだのを、彼が長袴を踏んだと感ちがいされ、六代目に叱られたが言訳け一つしなかったと私に語ったことがある。このあと、前進座に加入、そして兵役。双葉みどりは、岩手県一の関生まれの東北美人。昭和15年にミノルと結婚。昭和22年、漫才の相棒に困ったミノルが、当時漫才とはまったく無縁のみどりを説き伏せ、「1年間だけ」という約束で漫才をはじめた。ミノルの頭の光がなつかしい。
ただ、これは眉唾な点が多い。芸人特有の見栄もあるかもしれない。
相羽秋夫『上方演芸人名鑑』によると「浅草の寄席の息子」とある。また、桂米朝は『米朝・上岡が語る昭和上方漫才』でミノルからこんな話を聞いたと記している。
上岡 橘ミノル・双葉みどり、ここはNHKご推薦みたいなコンビでね、いわはったことをそのまま速記しても同じように読めるという漫才でした。
米朝 このミノルさんという人もちゃびんさんでね、頭がツルツルでした。これはどっちも東京弁なんですよ。ハイカラな感じでね。美男美女やった。末広以外にも東京の人形町に鈴本という寄席があったらしい。ミノルさんはそこの息子らしい。この人がね、シャギリ(寄席で開幕を知らせる太鼓)を打っているのを見たらね、打つ手が大阪と反対やった。つまり大太鼓と〆太鼓の置く位置が逆らしい。「東京は逆の位置なんで」とね。「東京のお方とは思ってましたけれども」「いや、 あっちの寄席へはあんまり行ってないんですけどね」と。それから、「実は人形町の末広とは別に鈴本という寄席があったンです。私の親父の代に潰してしまいましたけどねェ」と、そんな話をちよこっと聞いた。それで六代目尾上菊五郎が昭和五年に創立した日本俳優学校、むこうへ行ってンねん。
上岡それ聞きましたですよね、元・役者というね、なかなかシュッとしたいい顔でした。聞いた話ではヒトラーの横顔のマネをね、してたらしい。カツラをつけてね。
ただ、これは米朝の勘違いらしく(あるいはミノルが与太を言ったか)、ミノルと長い付き合いのあった秋田実は『アサヒ芸能』(1969年3月6日号)の連載『浪花芸人泣き笑い一代』で――
ミノルさんは大正三年、東京日本橋にあった水天館という寄席の席主の一人息子として生れた。だから小さい頃から寄席の芸人を見てきたので、芸道修業のむずかしさや苦しさは身にしみるほどわかっていた。だが、好きな道は仕方のないもので、旧制の中学校を卒業すると、両親の反対を押し切ってサッサと、六代目の尾上菊五郎が校長である俳優学校へ入学してしまった。
水天館は元々水天閣という寄席であった。悪く言えば端席で常打はせず、琵琶や邦楽、震災後は漫才などにも席を貸していた。これならばつじつまが合う。
なお、Wikipediaでは、「父は端席・人形町鈴本(末広とは別にあった。金馬が著書「浮世断語」で独演会をしたと語っている)の寄席の席亭であった。」などと書かれているが、これはとんでもない間違いで、人形町鈴本は名門の席であった点は指摘しておこう。
なお、ミノルが『笑根系図』の回答として送った経歴は以下のようなものであるという。
六代目尾上菊五郎校長の日本俳優学校本科二年中退(昭8)同年6月前進座に応募、中村浪之助の芸名にて中村鶴蔵の弟子分となり、(昭9)の2月退座、 同年6月より漫才に転向す。
幼い頃から芸に囲まれて育ったミノルであったが、それ相応の学校まで行ったという。横山ノック『知事の履歴書 橫山ノック一代記』によると、インテリな気配があったそうで――
橘ミノルさんという漫才師が、ハゲ直しの秘伝というものを教えてくれたのです。この人は橘ミノル・みどりというコンビを組んでいて、当時珍しい大学出で「インテリ漫才」ともてはやされた人です。
しかし、学業ではなく芸の道で生きる事に決めたらしく、歌舞伎の六代目尾上菊五郎へ入門。菊五郎が当時校長をしていた「日本俳優学校」へ入学することとなった。
日本俳優学校は1930年創設の歌舞伎俳優を中心とした専門学校で、尋常小学校卒業程度の学歴で入れる男女平等の学校であった。本科3年・研究科3年の計6年ある学校で、新しい歌舞伎学校として期待された――が、数年でつぶれた。
1933年、本科2年中退というところをみると、1931年に入学した模様である。
1933年6月、前進座の幹部・中村鶴蔵の弟子になり、「中村浪之助」と名乗る。屋号は「舞鶴家」。なお、歌舞伎の舞台経験は立派にあったようで『近代歌舞伎年表 大阪篇 第8巻』でもその名前を確認することができる。
しかし、役者生活は長く続かず1934年に退座。その後は演芸界に飛び込んだようであるが、その頃の動向は兎に角謎が多い。
さて、秋田実によると「前進座に入ってまもなく徴兵にあい、2年の軍隊生活を送った。その間に目に見えて髪が抜け落ちるようになり、役者を辞めた」という。髪が薄くなって役者として自信を持てなくなったのは大きいようである。
1930年代後半に千歳家歳男門下の千歳家アメオとコンビを結成。アメオは後に新山悦朗と名乗る。
1939年6月、アメオと共に中国慰問へ出かけている。当時の名簿が残っている。
⑪「陸恤庶發第六八八號 船舶便乗願ノ件申請」 昭和十四年六月三十日
一、往航 昭和十四年七月十一日宇品出帆(波ノ上丸)上海行
一、復航 〃 八月下旬 上海發宇品行
陸軍恤兵部主催 中支方面皇軍慰問團人名表(八名)
藝 目 藝 名 本 名 年 齢 住 所
漫談、司會 藤野城行 村崎勝行 二九才
三田耕子 同 二一才
日本舞踊 佐伯ミエ 佐伯三枝子 二二才
西洋舞踊 戸山恵以子 外山美代子 二三才
歌 謡 浦山和子 浦山あい 二三才
渡邊孝 渡邊孝一 二八才
ジャズ 渡邊ツギオ 渡邊次男 二六才
漫 才 橘ミノル 西村虎雄 二六才
戦時中は新興演芸部の若手として入社し、演芸部の劇場に出演。その礼儀の正しさからミスワカナからも信頼され「ミノルさんを見習え」といわれるほどであった。
1940年、双葉みどりと結婚をする。みどりは戦友の妹であったという。
新婚旅行では漫才の台本ばかり読んでいてみどりの方があきれたという伝説がある。
若手として売り出した矢先の1942年ころに召集令状が届いた。南方戦線へ送られたという。その後、除隊→再徴用を繰返し、復員したのは1948年春であったという。
1943年の帝都漫才協会にも参加している様子が確認できる(ただ、これは従軍事情は考慮されず、相方や身内が提出しても協会会員扱いとなったため、ミノルは戦地にいた可能性が高い)。
敗戦直前、アメオとコンビを解消し、大阪へ戻る(ただ、戦時中には既に京都へ住んでいた模様)。
1948年、双葉みどりとコンビを結成。みどりは「コンビは組みたくない」と言ったそうだが、「1年だけ」という約束で組まされた――と山川静夫などは記すが、秋田実は「みどりさんのほうからコンビ結成を申し出た」という。
同年、秋田實率いる「MZ研進会」に入会。夢路いとし・喜味こいし、島ひろし・ミスワカサ、秋田Aスケ・Bスケ、千歳家今若・今次、ミヤコ蝶々・南都雄二、山崎正三・都家文路が参加した。
戦後直後は秋田実の指示に従って地方巡業をもっぱらにしていた。
1950年代に松竹新演芸部が再興されると同部の所属となり、松竹系の劇場へ進出。
両人とも標準語を生かした漫才を得意とし、中堅の地位を得た。爆笑狙いの派手さこそないが、きれいで嫌味のない芸風はほっと一息つけるものだったのだろう。
ミノルが基本的にボケで、みどりがハスキーな声でツッコむという女性優位の漫才であった。ミノルは帽子やカツラをかぶって高座に出て、これをひょいと脱ぐと下が丸坊主なので客がどっと笑う――という一芸を持っていた。
私生活ではみどりは手芸――とこちらは普通の趣味を持っていたが、ミノルはタップダンス、占い、催眠術といささかスピリチュアルな趣味を持っていた。
特に催眠術は楽屋の評判だったようで、「催眠術で不眠が治った」という芸人もいたという。
占いでは姓名判断を活用したようで、戦後は「西村欣也」と自称していた。名簿などでは基本的にこの名前で記されていることが多い。
また、明朗で分かりやすい話術の持ち主だったこともあり、角座や松竹座の企画では司会として高座に上がることもあった。腰が低く、常識もあり、滅多に怒らないという気質もあり、楽屋では愛されたという。
その腰の低さは有名で、先輩にいびられまくっても一切怒号を漏らすことなく、「話し合いましょう」と敬語で相手を威圧した――という伝説さえ残る。
師匠分であった秋田實にして(『アサヒ芸能』1969年3月6日号掲載の『浪花芸人泣き笑い一代』)
誰が見ても後味の快い漫才で、ミノルさんの品のよさは、全漫才さんの間で定評があった。そして、その品のよさは、舞台の上だけでなく、楽屋ででも、家庭でも、少しも変りなく全く同じであった。
と褒められるほどの人徳であった。
1965年頃、関西演芸協会の幹事会計に就任。就任もその責任感の強さと頭の良さ、人徳が買われたという。
この頃、姓名判断に従って「立花ミノル」と改名している。
長らく上方漫才ブームを担う中堅として第一線で活躍していたが、1968年9月18日に心筋梗塞のために死去(吉田留三郎の調査による)。秋田実によると最後の仕事は「葬儀屋の慰安演芸会」であったという。『浪花芸人泣き笑い一代』に――
去年の九月、近所の葬儀屋の主人が、敬老の日のアトラクションを頼みに来た。ミノルさんは、会社を通さないヤミの余興は一度も行ったことがないので断った。が、近所のことではあり、老人を慰めることであるので、たっての頼みも断り切れず、
「それでは無料で出演しましょう。その代り、私の死んだ時は、葬式代を安くしてくださいね」
と冗談を言った。葬儀屋の主人も笑って、
「その時は、私もお礼に、無料で立派なお葬式をさしてもらいますよ」
その冗談が不幸にして本当になった。
敬老の日の三日後の九月十八日の朝、ミノルさんは心筋コーソクで、たった一日の患いで亡くなった。
とある。一度、心筋梗塞に倒れた際はまだ息があり、すぐさま病院に運ばれた。しかし、もう先は長くなかったようで、ミノルは付き添いのみどりに対し、
「苦労ばかりかけてすみませんでした。私が居なくなっても堂々と胸を張って世間に恥かしくない生活を送ってください」
と病床で語ったのが遺言となった。
夫を失ったみどりはミノルの母親と共に東京へ帰ったそうで、養母の孝養に勤めたという。1980年に『上方演芸人名鑑』が出たころにはまだ健在だった模様である。
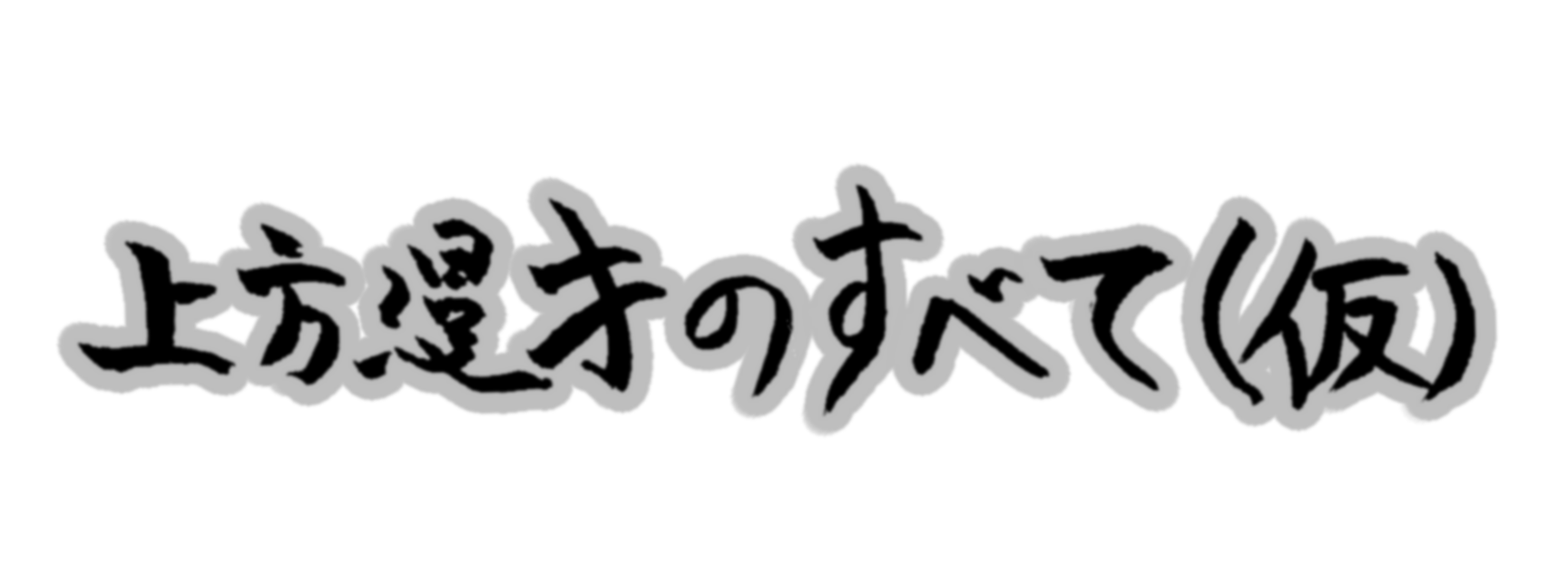


コメント