中山礼子(ロマンスレイコショー)

(左より)八多恵太・中山礼子・吉田奈良夫
人 物
中山 礼子
・本 名 中山 禮子
・生没年 1929年8月4日?~1982年10月12日
・出身地 熊本
来 歴
中山礼子は戦後活躍した浪曲漫才の大御所。女流浪曲師として出発し、後に「ロマンスレイコショー」を結成。男勝りの威勢のよさと美声で相手を圧倒する独特の浪曲漫才を培った。横山やすし・西川きよし結成のきっかけを作った人物でもある。
『新撰芸能人物事典明治~平成』では「1929年8月21日生まれ」とあるが、『文化人名録1963年度』では「昭和4・8・4 熊本」とある。
小学校卒業後、大阪の浪曲師・初代京山幸枝に入門。年の近い兄弟子に京山幸枝若がいた。『上方芸能』(1985年6月号)掲載の「浪曲研究会公演記録」によると――
〈芸歴〉昭和十七年初代京山幸枝に入門。十八年徳山市歌舞伎座初舞台。二十四年京山幸枝朗と名のり復帰。のち本名の中山礼子となる。
戦時中から女流浪曲の若手として売り出したが、一時期廃業。戦後に復帰して「京山幸枝朗」。後に中山礼子と改名する。
戦後は大和芸能社を経営していた田中定治郎の内縁の妻のような形となり、仕事と生活の両方を支えてもらっていたという。
若い頃には新国劇の作家をしていた倉橋仙太郎に可愛がられ、台本を提供してもらったこともある。遺稿集『幕のうちそと 故倉橋仙太郎の思い出集』の田中定治郎の寄稿に――
新国劇創立者、倉橋仙太郎先生と、昔、皆さまから承わった時。”あんな人が名人とは”と修業の足りない私には、何の感ずる事もなく打過した自分の心が、今更ながら恥かしく思います。女流浪曲家、中山礼子の支配人として大阪に家を持ち、落ちついた時、倉橋先生がおみえになりました。
”浪曲はいいですね。この乱れた世の中を建て直す元として浪曲は必要ですが、今日の行き方では歌謡曲や漫才に押されて浪曲は下火になりますよ。これからの浪曲を背負って立てるのは、礼子、貴女ならやれると思って尋ねて来ました。
汽車を電車が普通にレールの上を走っておれば人は見ませんが、一旦脱線すると黒山の人だかり。舞台の芸もその通り、真剣に思い切った芸をやるのです。ネ、突然おじゃましてこんなことをいうと、倉橋はちよっと頭が変になっておるんじゃなかろうかと思いなさるでしょう、ネ”
”いいえ、いいえ、先生の仰言る通りですよ”と返答はしたものの、何がなにやらわからぬままその日は先生とお別れしましたのが今から十七年前のこと。倉橋先生と言葉を交したのが田中定治郎として初めての事でした。
”あのおっさん、少々頭が変だな?”と思ってお別れしましたが、先生の仰言った通り、浪曲は淋しくなりました。先生の頭に狂いはない。くるった頭の持主は田中定次郎でした。
国定忠治赤城山
月、一つ、
土、
という台本をお書きになって、礼子さんに一口々々教えてくれました。礼子さんもよく勉強しましいち時の中山礼子の芸は生きていて、十三のOK劇場で設曲大会があって、土を口演した時は、 自分の芸に自分自身が食われたほどに中山礼子の芸は真剣でありました。
事情がありまして礼子は私から離れてゆき、今はどんな芸を舞台で演じております事やら、私の耳には這入って来ませんが、あの頃の芸が礼子さんの舞台にあれば、亡くなられた先生の芸で懐く聞かせて頂けるものにと思う程、倉橋先生は名人でありました。
1953年頃より民間放送に出演するようになり、『かりがね草紙』『晴姿上州男』など、侠客物を中心に演じている。
また、1954年頃には部落解放団体と結託し、同年におこった「奈良硫酸事件」を浪曲にして女性の無実を訴えるなど、社会的な浪曲を演じていた時期もある。
1950年代後半まで浪曲界の花形として第一線で活躍を続けていたが田中定治郎と破局した事や浪曲人気の下火などもあり、浪曲以外の道を模索するようになった。
1962年、歌謡曲一座で司会漫才をやっていた中山恵一・修を引きこみ、「ロマンスレイコショー」を結成。自身は三味線を持ち、恵一・修にギターを弾かせる歌謡浪曲漫才に転身した。この転身に際し、長年奉公していた大和芸能・一二三芸能社から松竹芸能へと移籍している。
1963年頃、中山一郎(吉田奈良夫)が参加。
当時の浪曲漫才ブームということもあり、早くから角座などに出演。一方、松竹はライバルチームが多かったこともあり、1964年頃に吉本へ移籍している。
吉本では浪曲漫才の大看板として君臨。早くから一枚看板の地位を与えられたという。
1966年1月、吉本新喜劇の研究生をしていた西川きよしに、「横山やすしさん、コンビと別れるから一ぺん会ってみえへんか」と声をかけた。
きよしは中山礼子に従ってやすしと出会い、後に「やすし・きよし」を結成する。きよしはこのことを今も感謝しているようで「やすしさんに会わせてくれたのは中山礼子さん」と自伝の中でも記している。
浪曲ショー時代は『国定忠治』『ぶらり大阪』など浪曲を生かしたボリューミーな芸を得意とした。中山礼子が浪曲とツッコミで、恵一が大ボケ、一郎が中ボケというような役回りであったという。
1973年に一郎が抜けたため、恵一とのコンビになる。これに伴い、「ロマンスレイコショー」の名称はやめ、「中山礼子・八多恵太」と改名した。
長らく吉本の第一線で活躍し、戦後の勃興を模索する吉本の屋台骨として活躍した。
一方、後年は浪曲が余りウケなくなったこともあり、浪曲の部分を減らし、恵太とのしゃべくり漫才となった。
しわがれ声の恵太が男勝りの礼子を徹底的にいびり、礼子が怒鳴り倒す、それを恵太がさらにあおるというトムとジェリーのような漫才を演じた。
一方、機会があると浪曲漫才や河内音頭を披露することもあり、こちらで往年の美声を響かせることもあった。夏場は礼子が河内音頭を受け持ち、大喜利で演じることもあったという。
礼儀作法にはうるさかった一方で頼れる姉御肌でもあり、いいと思った芸人を吉本幹部に推挙するなど義侠心のある姉御であった。
1979年冬、少年音頭取りとして活動していた河内家菊水丸に声をかけ、吉本に引き込んでいる。河内家菊水丸は「中山礼子師匠によって吉本に入れた」と色々な記事に記している。
1981年9月、なんば花月において「中山礼子芸能生活四十周年記念リサイタル」を開催。
MANZAIブームで吉本も盛り上がりを見せ、円熟した芸を見せようとした矢先の1982年10月、心臓病に倒れた。
10月5日にまでなんば花月に出ていたものの、間もなく心不全を起こし卒倒。病院に運ばれたものの、息を引き取った。
『月刊浪曲』(1982年11月号)の訃報欄に――
訃報
中山れい子師死去
中山れい子
昭和57年10月12日午前6時35分、急性心不全のため入院中の大阪市天王寺区大阪赤十字病院で死去、行年53歲。
10月5日まで元気にナンバ花月の舞台を勤めていた。
相方の死にガックリ来たのか八多恵太は元気を亡くし、1984年に後を追うように亡くなっている。
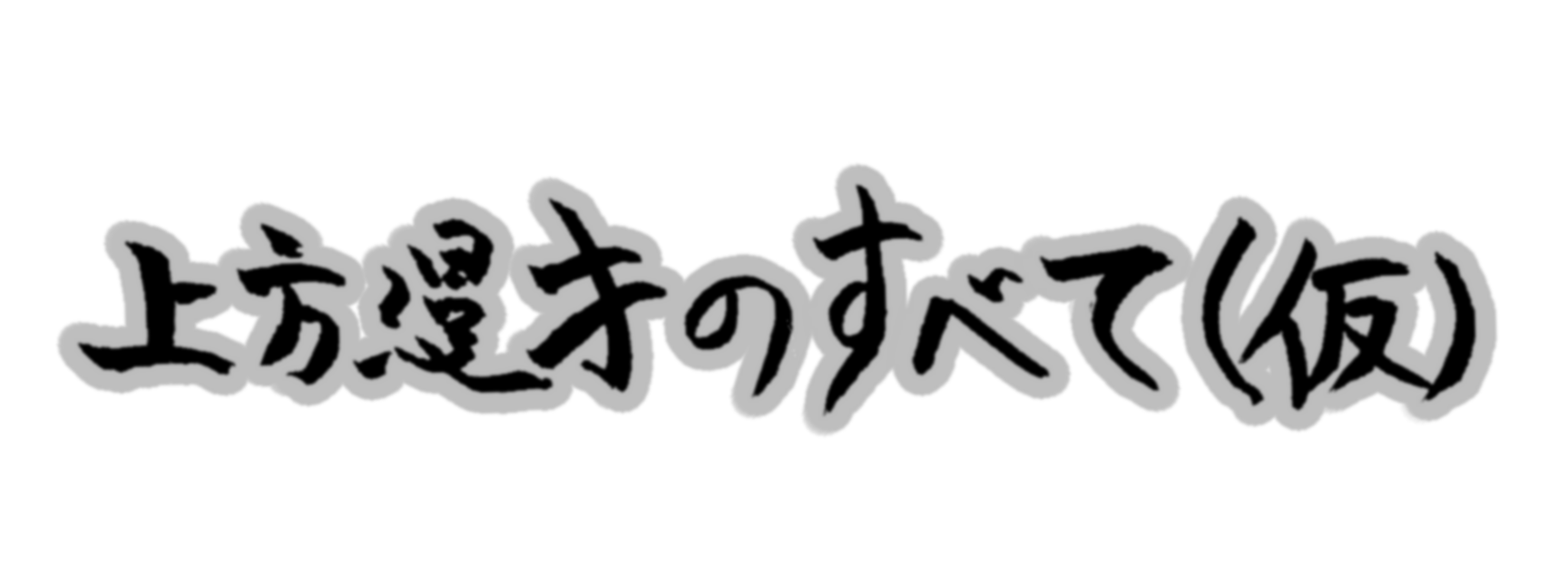


コメント